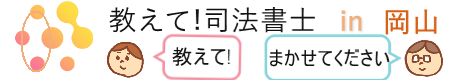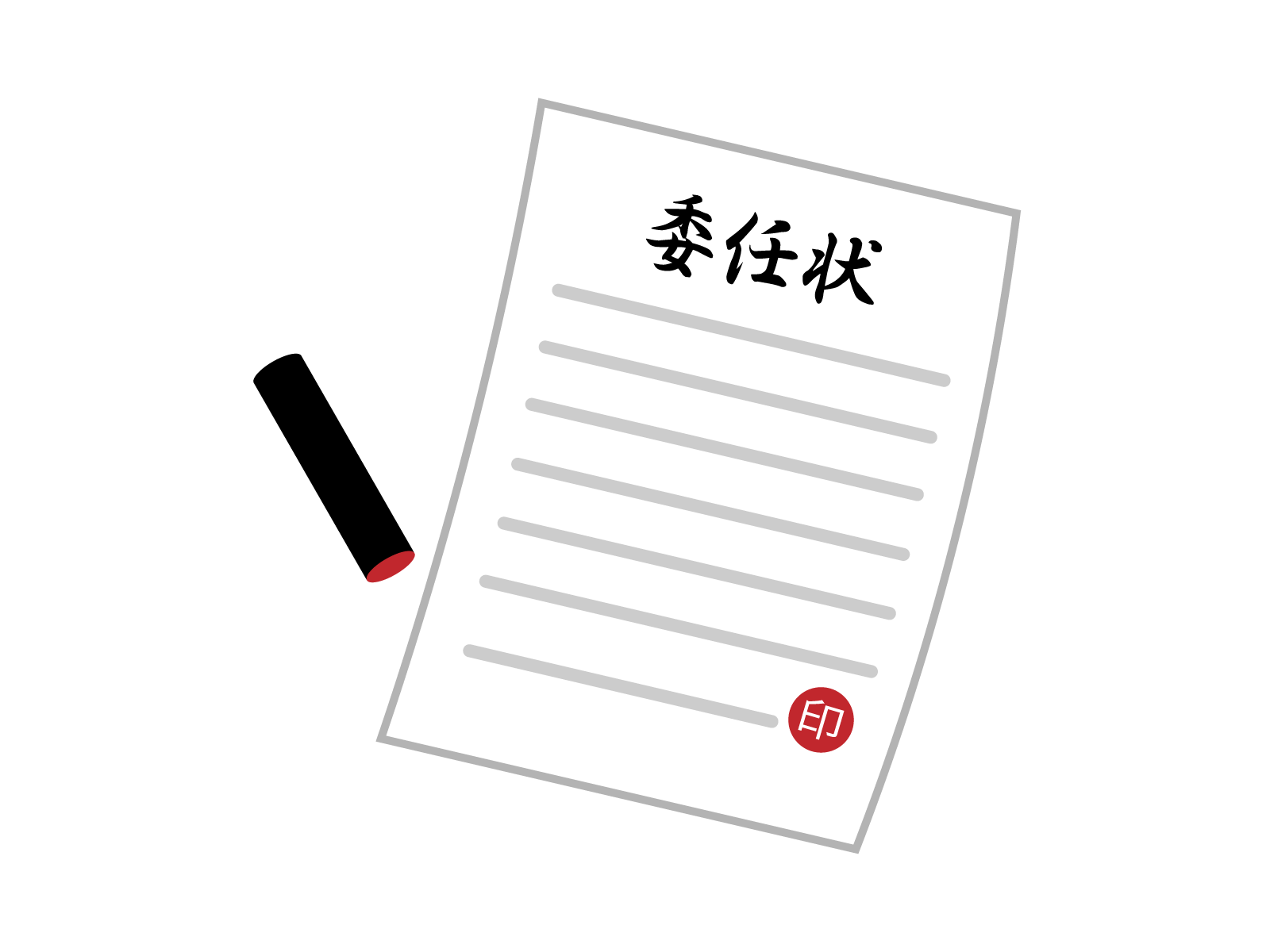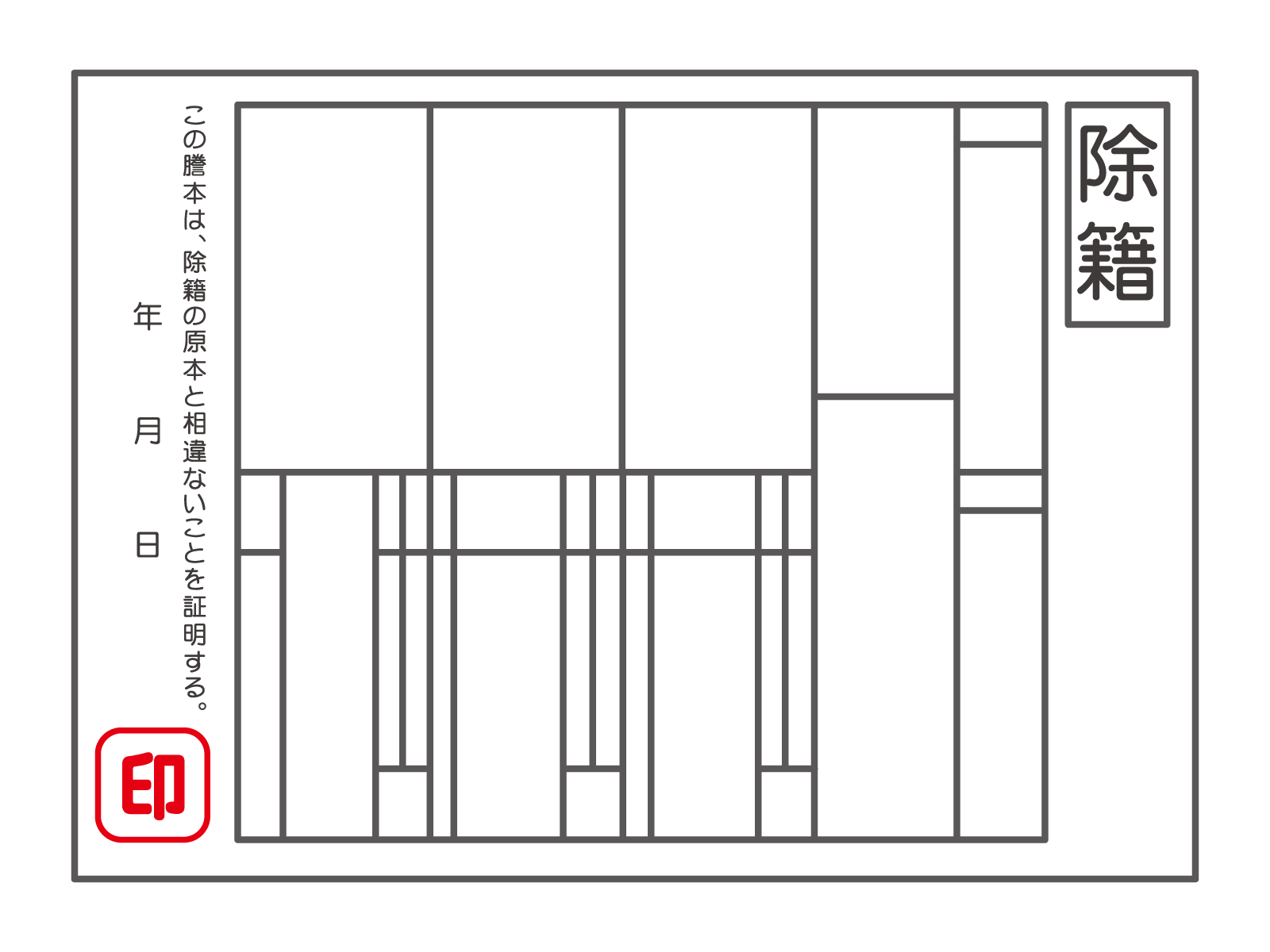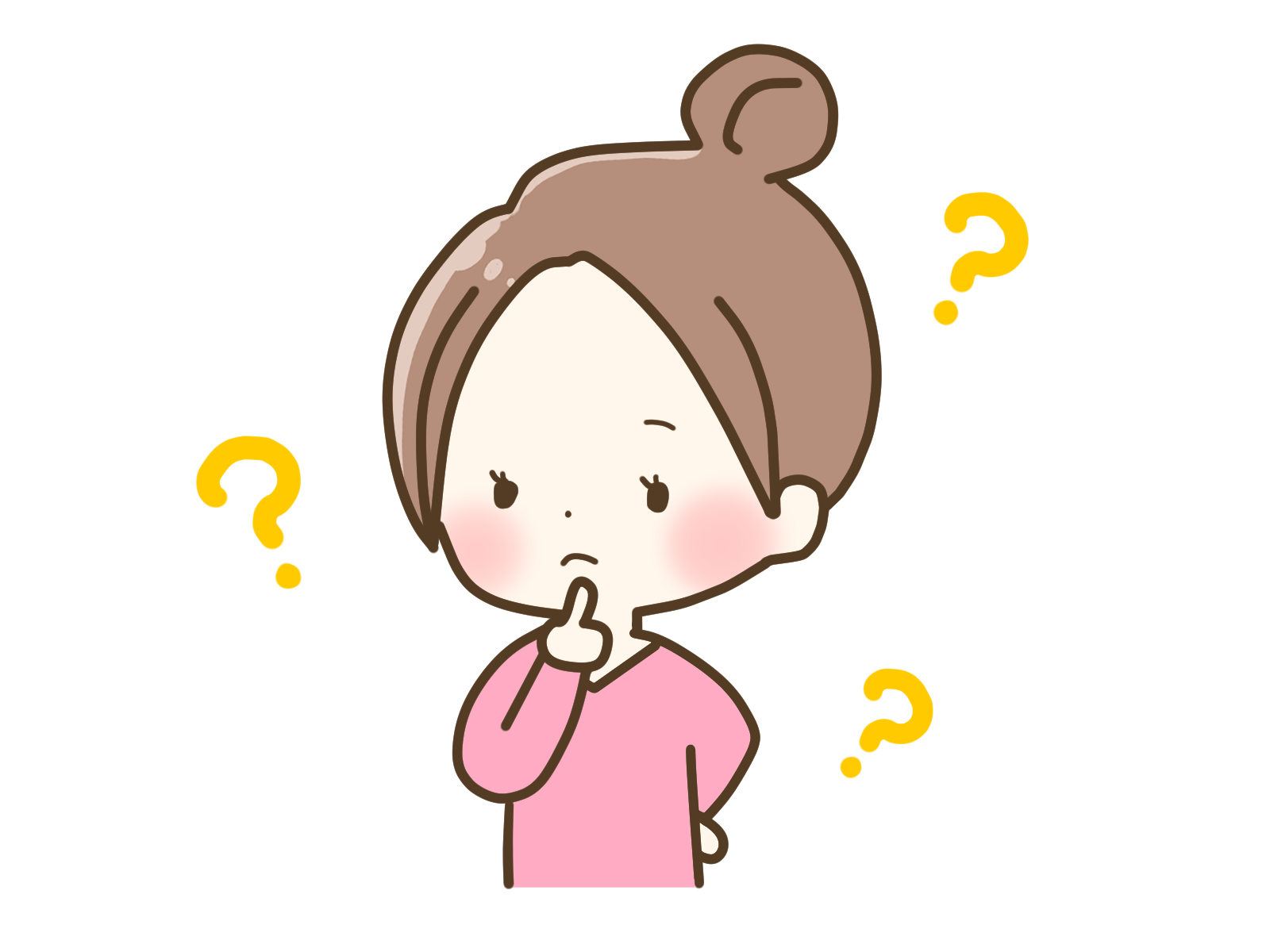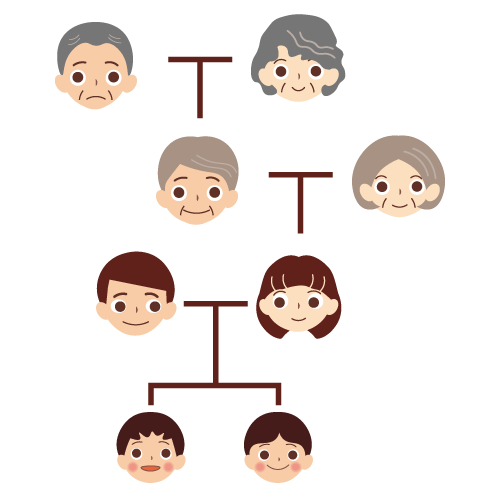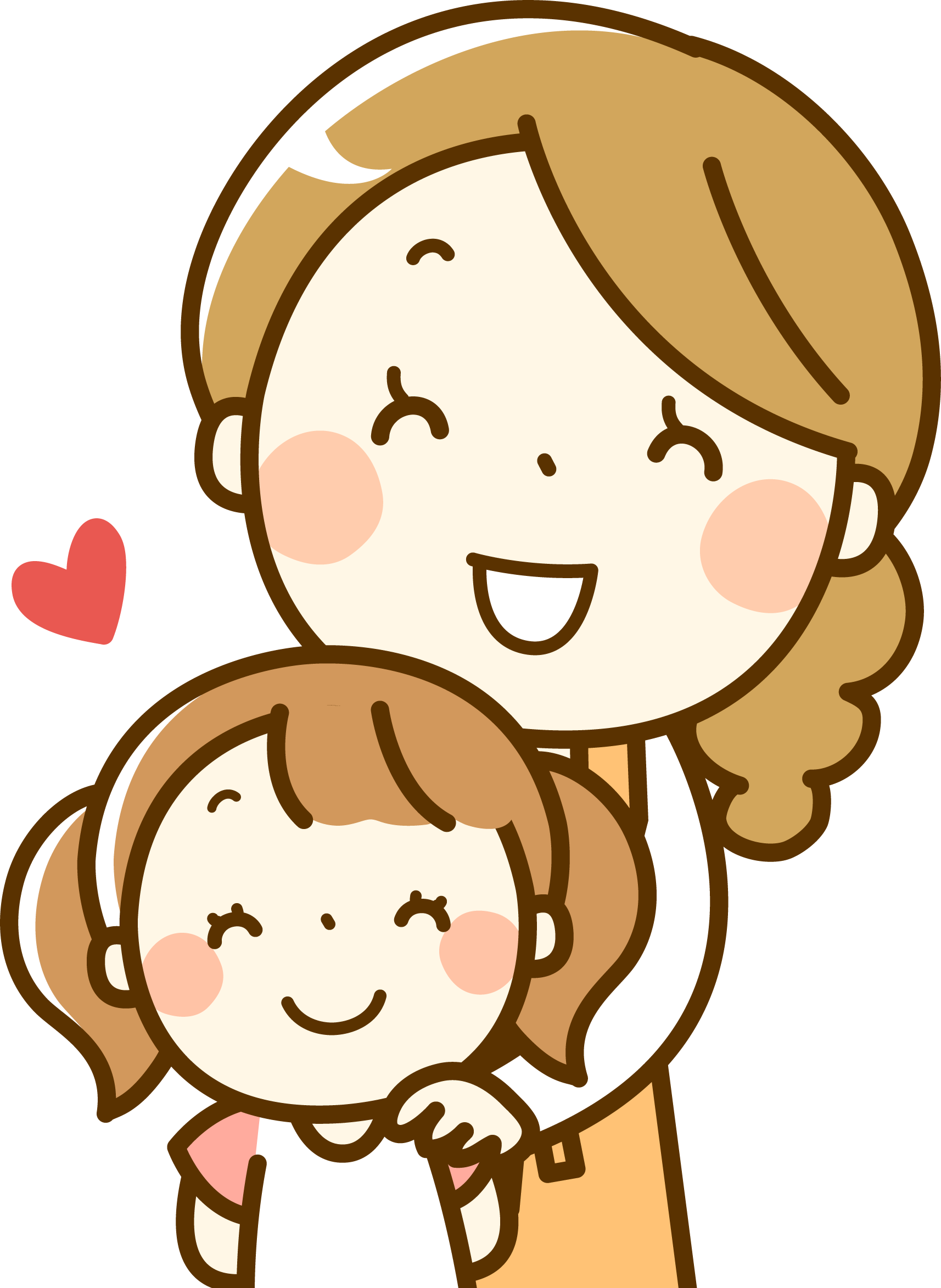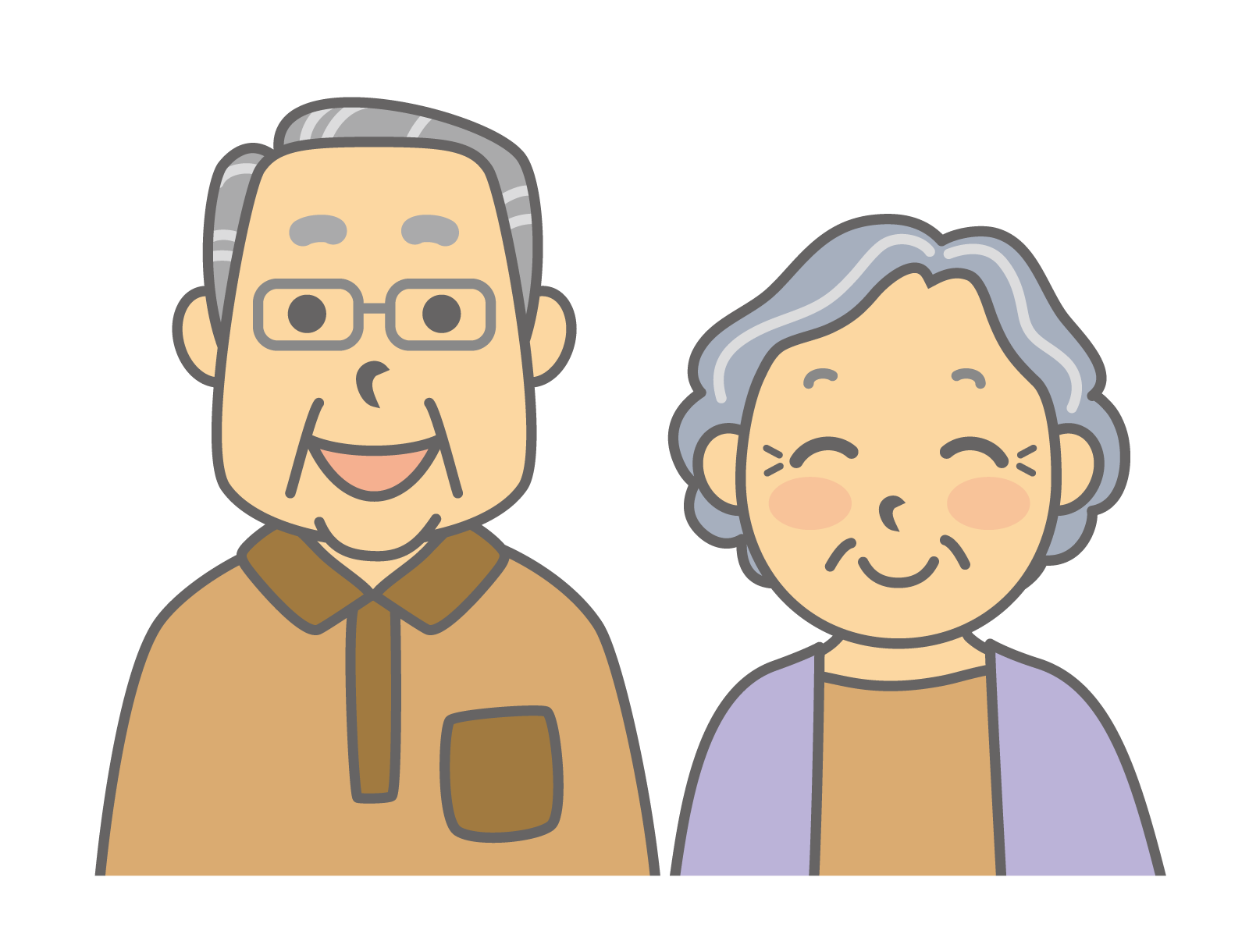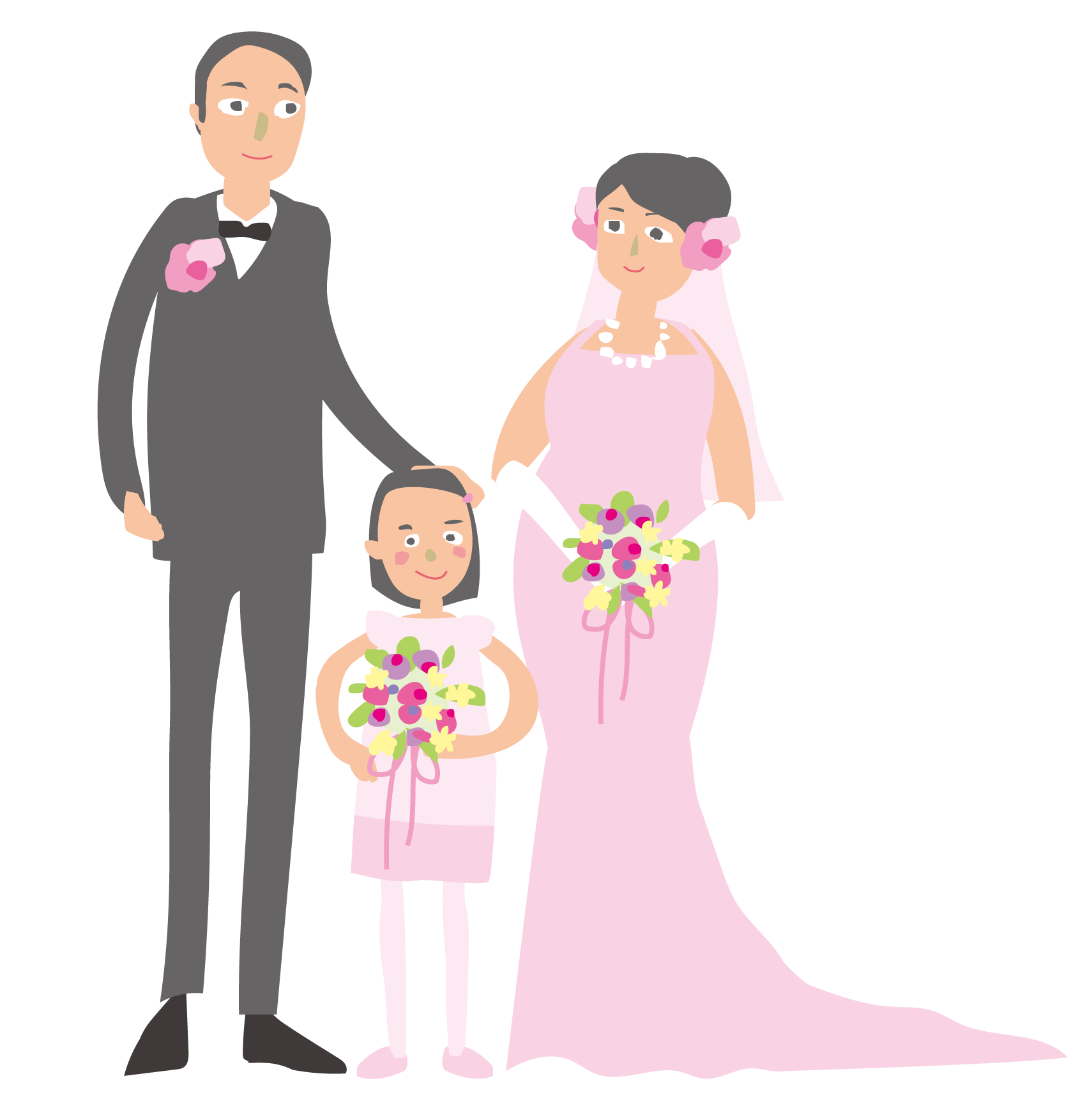相続放棄すると相続税の基礎控除の計算をするにあたり何か影響がでるのか?(in 岡山)

A子さん
相続放棄すると相続税の基礎控除の計算に影響があるの?

にしこり
何もありません。
相続放棄した者も法定相続人として数えるので、相続放棄しても相続税の基礎控除で不利になることはありません。
最近、103万円の壁(年収が103万円以下であれば、所得税はかからない)の撤廃について報道されています。
所得税と同様に、相続税も、相続財産がある一定額以下であればかかりません。
その一定額を基礎控除額といい、下記の計算方法で算出できます。
3000万円+600万円×法定相続人数
例えば、法定相続人が配偶者、長女、長男の3人だった場合、相続財産が4800万円(=3000万円+600万円×3人)までは相続税はかかりません。

にしこり
相続税は、相続財産が基礎控除額を上回った部分にかかる税金です。
ここでいう相続財産には、仏壇、仏具のような非課税財産は除かれます。
また葬儀でかかった費用はマイナスします。
逆に、相続などにより財産を取得した人に対してした3年以内(令和6年1月1日に7年に改正)の生前贈与はプラスします。
また、死亡保険金、死亡退職金も非課税枠を超えた部分は、プラスします。
相続放棄をしても相続税の基礎控除の計算をするにあたり何も影響がない
相続放棄をした者は、もともと相続人ではありません(民法939条参照)
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
しかし、基礎控除額を計算する場合においては、相続放棄した者も法定相続人として数えます。
例えば、法定相続人が配偶者、長女、長男の3人だった場合、長女が相続放棄しても、相続財産が4800万円(=3000万円+600万円×3人)までは相続税はかかりません。
つまり、相続放棄をしても相続税の基礎控除の計算をするにあたり何も影響がでません。
相続放棄をした場合の死亡保険金、死亡退職金の非課税枠について
死亡保険金、死亡退職金※は、受取人の固有の財産なので相続税とは関係なさそうにみえますが、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
※勤務先が、退職金規定に、死亡退職した従業員に退職金を支払うことを定めている場合は、受取人に死亡退職金が支払われます。

にしこり
受取人の固有の財産は、故人の預貯金や株などの相続財産と違い、遺産分割(遺産分け)の手続きを経ずに受取人は取得できます。
ただし、冒頭で説明したように、死亡保険金、死亡退職金ともに非課税枠(500万円×法定相続人数)があります。
基礎控除額を計算する場合と同様に非課税枠を計算するにあたり、相続放棄した者も法定相続人として数えます。
ただ、注意してほしいことがあります。
それは、相続放棄をした人が死亡保険金、死亡退職金を受けとる場合、非課税の適用(500万円×法定相続人数)を受けることはできないということです。(相続税を計算するにあたり死亡保険金、死亡退職金全額をプラスします。)
- 相続放棄をしても相続税の基礎控除の計算をするにあたり不利になることはない
- 相続放棄をしても死亡保険金、死亡退職金ともに非課税枠に影響がないが、相続放棄をした人が死亡保険金、死亡退職金を受けとる場合非課税の適用を受けることはできない
最後まで読んでいただきありがとうございました。