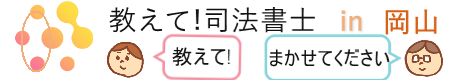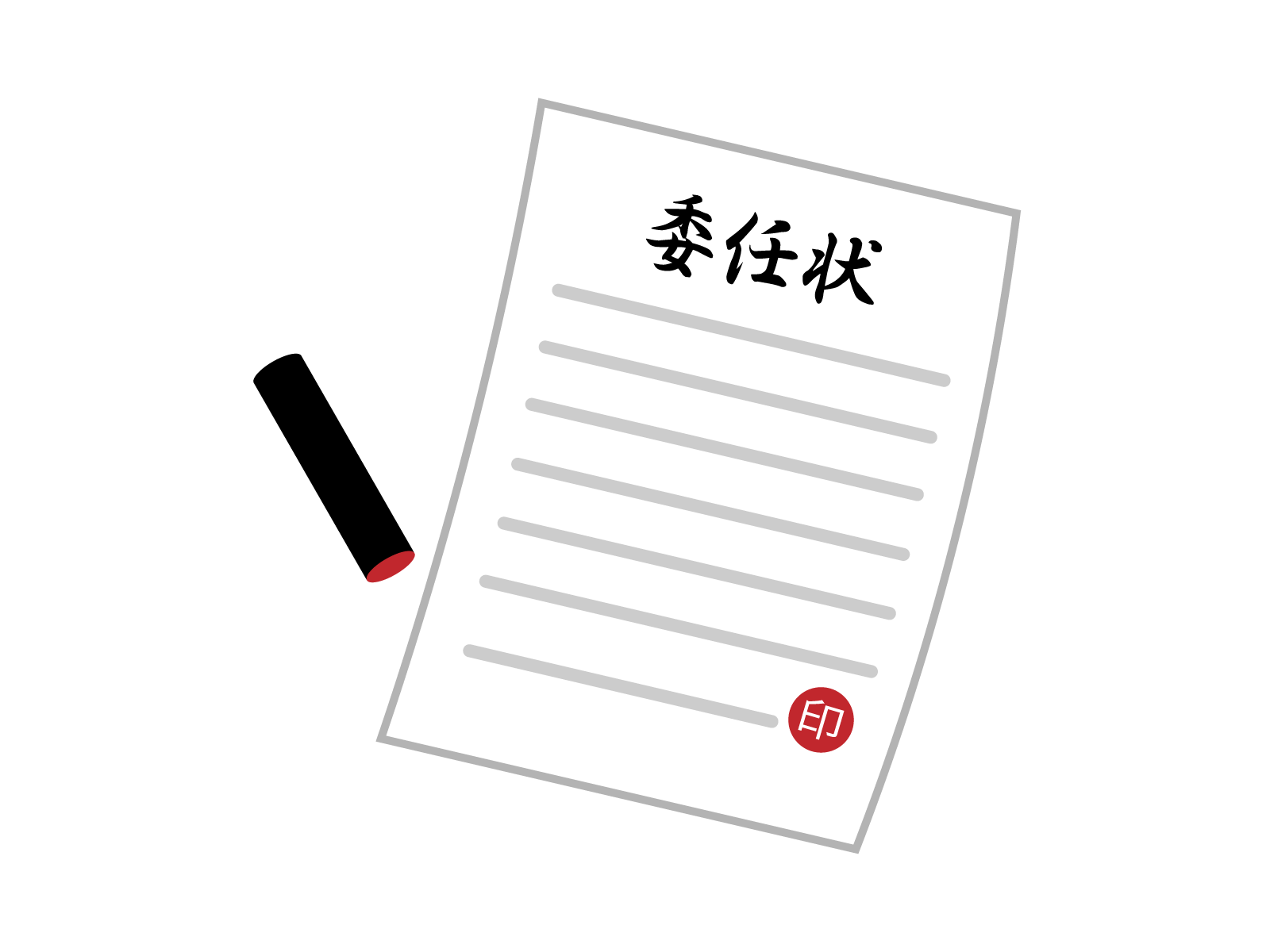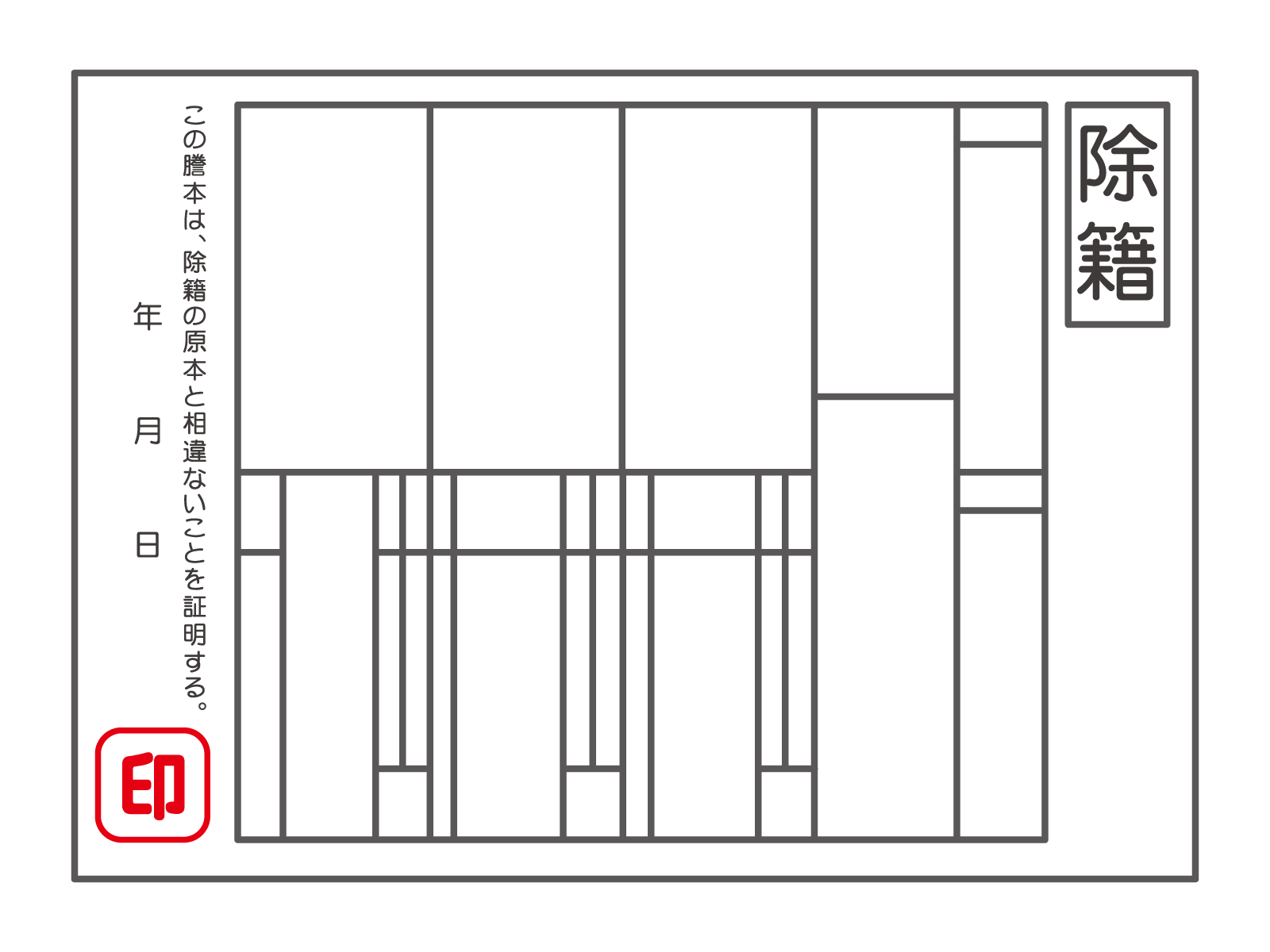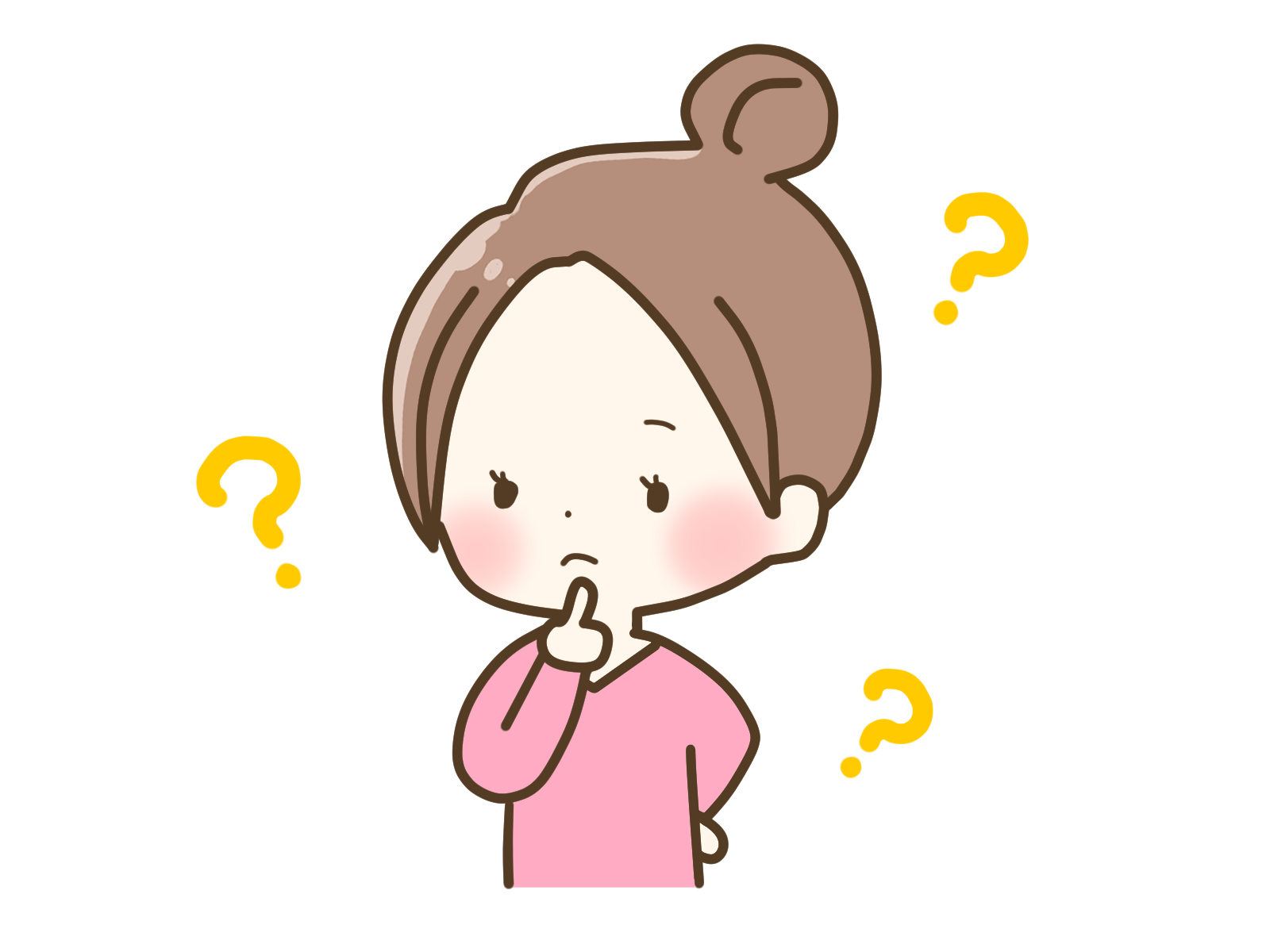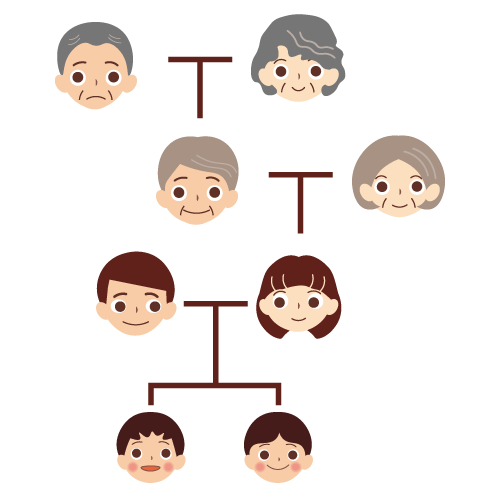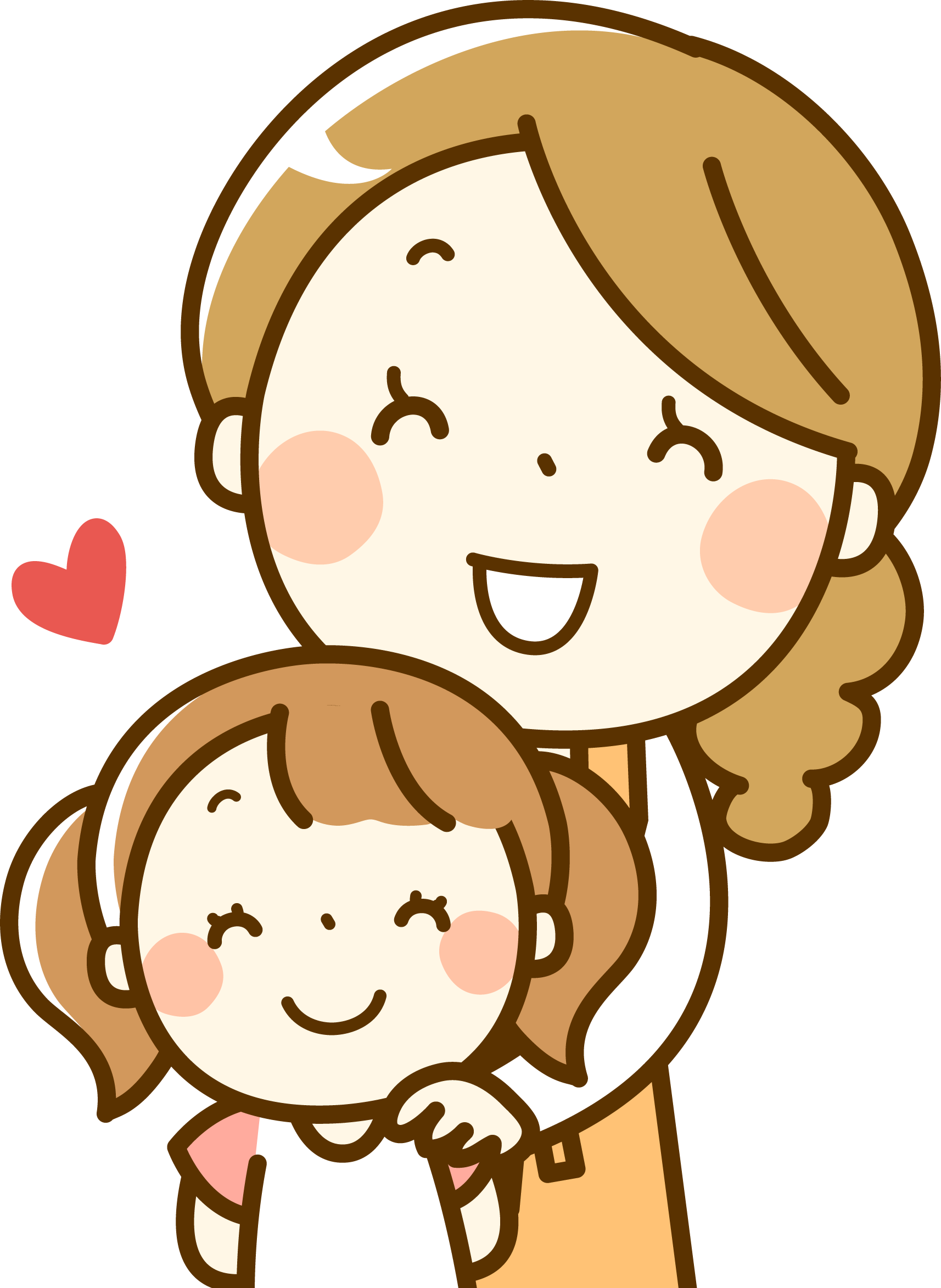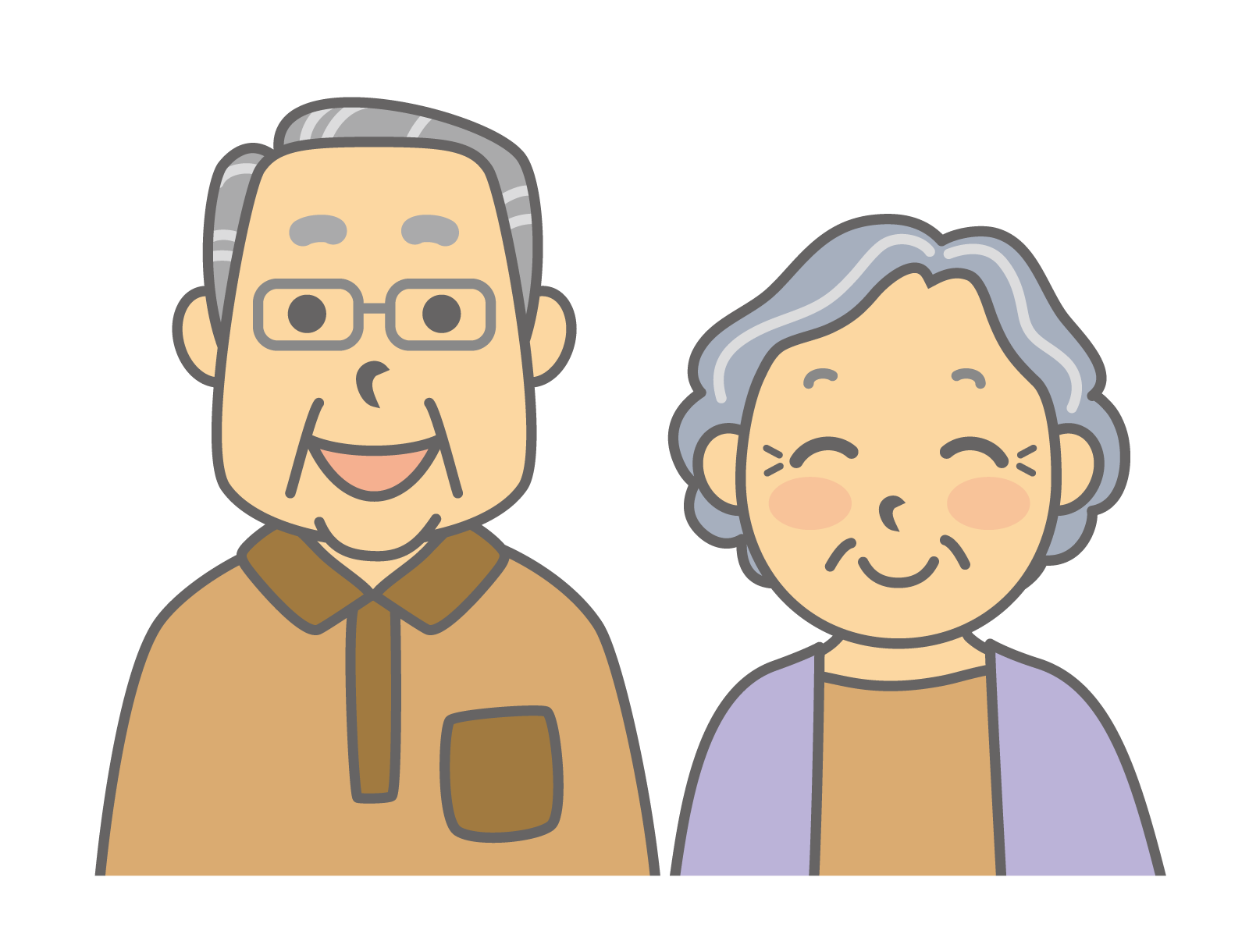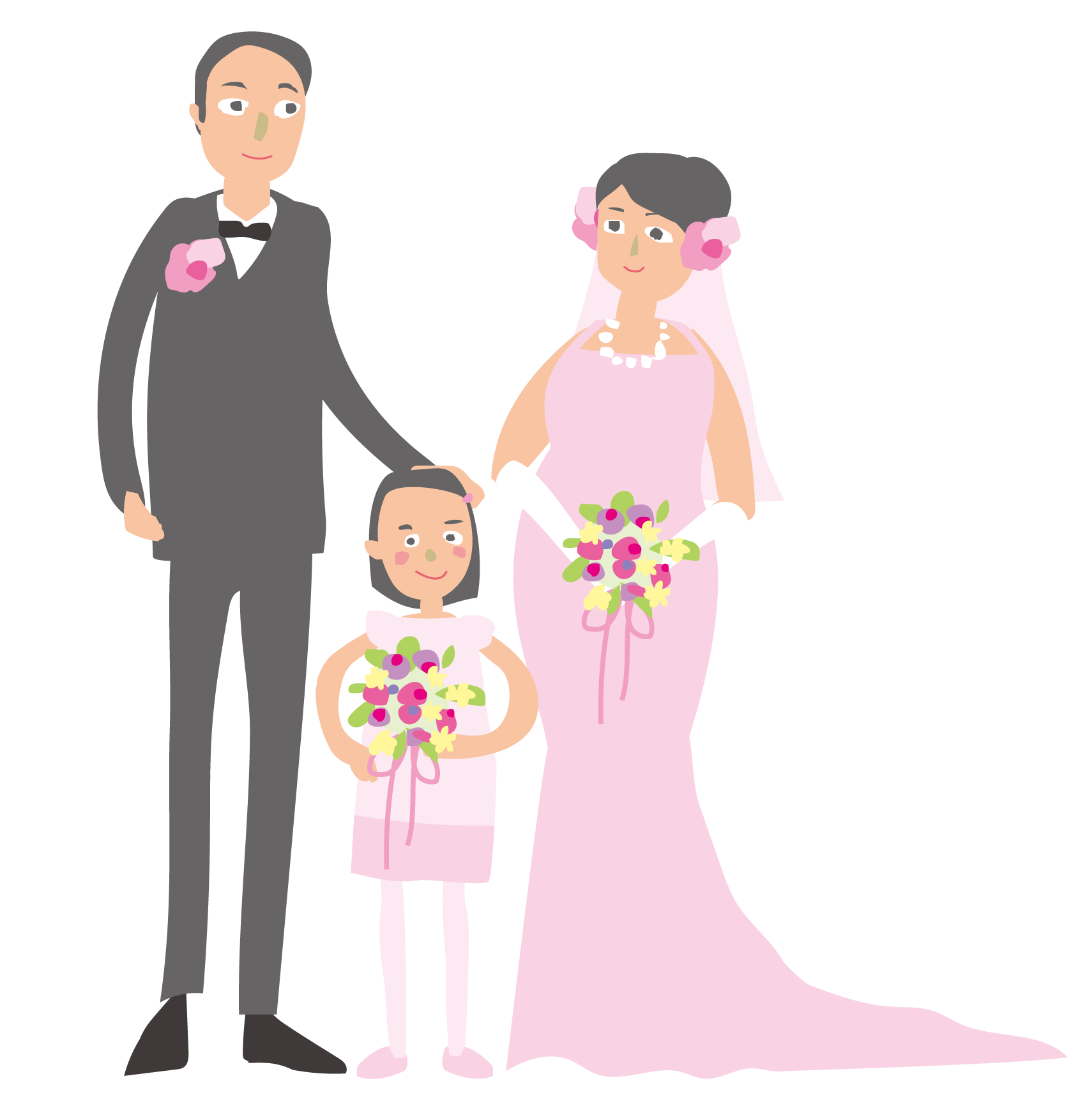戸籍謄本等に載っていない人が相続人になるケースがある(in岡山)

A子さん
相続人ってどうやって調査するの?

にしこり
故人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得すれば、相続人は分かります。
しかし、故人が亡くなった時点で、戸籍謄本等に載っていない人が相続人になるケースがあります。
相続人を調査するにあたり、日本の戸籍制度は本当によくできています。
故人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得すれば、相続人が誰かが客観的に明らかになるからです。
しかし、故人が亡くなった時点で、戸籍謄本等に載っていない人が相続人になる場合があります。
それは、遺言による認知と死後の強制認知です。
戸籍謄本等に載っていない人が相続人になるケース
遺言による認知、死後の強制認知を説明する前に、少し認知についてみていきましょう。
認知は、婚姻外の子(親が結婚しないで生まれた子)を自分の子と認めて法律上親子関係を生じさせる行為です。
男(父)※が子を認知をすることによって、相続や扶養などの権利義務が発生します。
※母は、分娩の事実によって親子関係が当然に発生するので、認知は不要と解されています。
逆に、生理的に血が繋がっていても、認知をしなければ、子は父を相続することができません。

にしこり
認知は、戸籍法に定める届出(市区町村役場に認知届を提出)により行います。
愛人に対して、「子どもを認知する」と口頭で伝えただけでは、認知したことにはなりません。
遺言による認知
認知は遺言によってもすることができます。(遺言書に「〇〇を認知する」と記載します)
なぜ、生前に認知をせずに、遺言による認知を選択するのでしょうか?
それは、生前の認知により愛人の子の存在がばれて、妻と揉めてしまうことを避けるためです。

にしこり
認知届が受理されると、男の戸籍に、「認知日」「認知した子の氏名」「認知した子の戸籍(愛人の戸籍の情報)」が載ります。
遺言による認知の場合、遺言執行者(遺言の内容を実現する人)は、その就職の日から10日以内に市区町村役場に認知届を提出しなければなりません。
遺言による認知は、亡くなってから認知届を提出するまでにタイムラグがあるので、故人が亡くなった時点で、戸籍謄本等に載っていない人が相続人になります。
死後の強制認知
強制認知とは、子ども側から認知を強制することです。
例えば、男と愛人の間に幼少の子がいて、男が認知しない場合、子ども側(子の法定代理人)から訴えを提起して、認知を強制することができます。
男が生存中であれば、いつでも訴えを提起することができます。
しかし、男が亡くなった後は、死亡の日から3年間に限り、認知の訴えを提起できます。(死亡を知った日から3年間ではありません。)
男(父)が亡くなってから3年以内に強制認知の訴えを提起し、認知が認められ、判決が確定すると、愛人の子は相続人になります。
この場合も、故人が亡くなった時点で、戸籍謄本等に載っていない人が相続人になります。

A子さん
遺産分割をやり直す必要があるの?
亡くなってから2年と数か月も経っていれば、通常は、遺産分割(故人の遺産分け)も済んでいるでしょう。
そのため、死後の強制認知は、認知前にした遺産分割は無効になりません。
認知された子どもは、他の相続人に対して、自分の取り分について価額のみの支払を請求(金銭を請求)するにとどまります。

にしこり
遺産分割(故人の財産の遺産分け)は、相続人全員でする必要があります。
相続人が1人でも欠けていた場合、その遺産分割は無効です。
生前に認知された、または、遺言によって認知された愛人の子を無視して、遺産分割をしても無効ですが、死後の強制認知の場合、認知前にした遺産分割協議は、認知された子は関与していませんが、無効になりません。
その他の認知
せっかくなので、最後に少し変わった認知をみていきましょう。
成年の子を認知する場合
成年の子(成人した子)を認知しようとする場合、成年の子の承諾が必要です。
成年の子の承諾なく認知を認めてしまうと、子は幼少期、少年期扶養されなかったのに、親が年老いたときに、親を扶養をしなければなりません。
親が資産家で、それなりの財産を相続できる場合は別ですが、自分は何もしてもらえなかったのに、老後の面倒だけを押し付けられるのは子にとってあまりにも理不尽です。
未成年者が認知する場合
未成年者が子どもを認知する場合は、法定代理人(通常は、ご両親)の同意は不要です。
認知は、何より認知する本人の意思が大事であり、尊重されるべきなので、同意になじまないからです。

にしこり
ちなみに、未成年者が法律行為をするには、原則、法定代理人(通常は、ご両親)の同意が必要です。
例えば、高校生がバイクを購入する場合、ご両親の同意が必要になります。
法定代理人の同意が必要な理由は、知識、経験や判断能力が乏しい未成年者※が不利益を被らないようにするためです。
※ただ、高校生位なら、普通の大人より知識が豊富で判断能力が優れている人もいますが・・・
死亡した子を認知できる場合
死亡した子を認知することができません。
認知しても意味がないからです。
しかし、死亡した子に子がいる場合は、死亡した子を認知できます。
なぜなら、孫(死亡した子の子)は、親(認知した人)について代襲相続が可能であり、また親(認知した人)に扶養を求めることができるからです。
- 遺言による認知と死後の強制認知は、故人が亡くなった時点で、戸籍謄本等に載っていない人が相続人になる
- 死後の強制認知は、認知前にした遺産分割は無効にならない
最後まで読んでいただきありがとうございました。