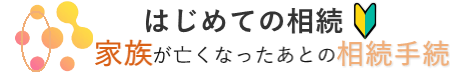故人が、賃借りしていた部屋の手続
故人が部屋を賃借りしていた場合、一緒に住んでいた相続人は、どのような手続をとればよいでしょうか?
- 「民間の賃貸」か「公営住宅」か
- 「引き続き居住する」か「引越しをする」か
で手続方法が異なります。
もし、引き続き居住したい場合は、相続人は、『民間の賃貸マンション・アパート』には、住み続けることは可能です。
しかし、『公営住宅』には、原則、住み続けることはできません(ただし、例外あり)
民間の賃貸マンション・アパートの場合
住み続ける場合
部屋を賃借りする権利(賃借権)は相続の対象なので、相続人は引き続き部屋に住み続けることができます。
管理会社または大家に連絡して、『賃借人が亡くなった旨と、引き続き居住したい旨』を伝えます。
相続人が複数いる場合は、誰が賃借権を相続するか(新しい賃借人になるか)を話し合って決めたのち、管理会社または大家に連絡します。
賃貸借契約の更新の際に、新賃借人(相続人)は賃貸借契約を結べばよいので、相続のタイミングで、新賃借人(相続人)は賃貸借契約を結ぶ必要はありません。
誰も住まない場合
誰も住まないのであれば、相続人は、管理会社または大家に連絡して『解約※する旨』を伝え、解約手続(部屋の明渡し、鍵の返却、未払家賃の支払、敷金の返還等)を行います。
※賃貸借契約では、『契約期間(たいていは、2年間)の途中でも、1か月前までに、解約の申し入れをすれば賃貸借契約を解約できる』旨の取り決めがされていることが一般的です。
公営住宅の場合
原則、同居人は公営住宅に住み続けることはできない
公営住宅を使用する権利は相続の対象ではないので、賃借人が亡くなってしまった場合、原則、同居人は住み続けることはできません。
一定の猶予期間内に住居から退去しなければいけません。
(猶予期間は、都道府県、市区町村によって異なりますが、おおよそ3か月~1年程度です。)
退去する場合は、公営住宅の管理事務所等(管理センター等)に退去届を提出して、解約手続(部屋の明渡し、鍵の返却、未払家賃の支払、敷金の返還等)を行います。
例外的に、同居人が公営住宅に住み続けることはできる場合
ただし、公営住宅の管理事務所等(管理センター等)に使用継続申請書を提出し、県(県営住宅の場合)や市(市営住宅の場合)等の承認を受けることにより、同居人が賃借人となり、引き続き住み続けることができる場合があります。
どのような同居人が承認を受けることができるかは、各自治体の条例によって異なりますので、県や市などに確認しましょう。
下記の同居人は承認を受けて、引き続き住むことができます。
- 配偶者(ただし、公営住宅に入居後に婚姻した場合、1年以上同居している必要があり)
- 内縁関係にある方(1年以上同居している必要あり)
- 60歳以上の親族
- 一定基準以上の障がいを持つ親族
ただし、一定基準以上の収入がある場合や、家賃を3月以上滞納している場合など一定の要件に該当する場合は、承認を受けることができない場合があります。
同居人が亡くなった場合
賃借人ではなく、同居人が亡くなった場合は、公営住宅の管理事務所等(管理センター等)に異動届を提出します。
提出期限は、各自治体によって異なります。
(例えば、岡山市の場合、死亡してから2週間以内)